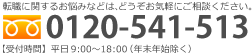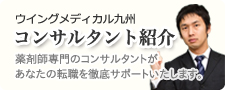1097) 長いお別れ
「長いお別れ」という小説を一気に読み終えた。認知症という誰のところにでも訪れる可能性のある病気、いつ訪れるか分からない病気、現在の医学では進行をゆっくりさせることは出来ても治すことの出来ない病気、そんな一筋縄ではいかない、やっかいな病気をテーマにした小説である。作者は直木賞作家である中島京子氏。
作者の父、フランス文学者だった父親がアルツハイマー型認知症と診断されてから、亡くなるまでの10年間の自らの介護体験をベースに、患者とその家族の日々をユーモアを効かせて描いている。作者は、住まいが実家に近かったこともあって、介護する母親の手伝いによく通っていた。そのため徐々に病気が進行してゆく父親の姿を間近で見ていて、認知症にはそれまで想像もつかなかったような興味深い症状があることに気付く。そんな出来事をその都度メモしていったのが、小説の母胎になったということだ。
ちなみに認知症のことを別名「長いお別れ」と呼ぶらしい。少しずつ記憶を失くしながら、長い時間をかけてゆっくりゆっくり周囲の者から遠ざかってゆくのがその別名の由来らしい。小説の中に出てくるエピソードである。
登場人物は、小説の中では中学校の元校長先生として登場する父親と、その介護に懸命な母親、3人の娘とその家族たち(夫や子供、恋人など)、父親の同窓生や元同僚、介護施設の職員たち、と広範におよび、様々な事件が起きて退屈させない。
読んで面白かったと言ったら罰が当たるだろう。しかし認知症という深刻な病気をテーマにしながらも、読んでいて気持ちが落ち込むことはなかった。随所に散りばめられたユーモアとさすが直木賞作家の筆力によるものだろう。将来を考えると色々と示唆に富んでいて、役に立つことが多かった。認知症がどんな様相を示しながら進行してゆくのかということもある程度認識出来た。いい本に出会ったと思う。(2017.09.04)
画像 : 水彩画教室、先週の作品 「木橋」